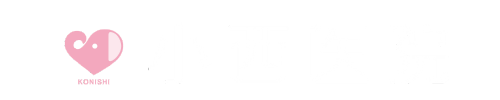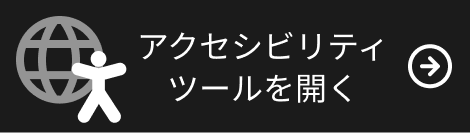- HOME
- 循環器内科・内科
高血圧症
高血圧症は、原因となる病気が特定できない本態性高血圧症と、腎臓病、内分泌異常、血管異常など、原因となる病気が明らかな二次性高血圧症に分けられ、本態性高血圧症が大部分(90%以上)を占めます。ここでは、本態性高血圧について説明します。血圧とは、心臓から送り出された血液が血管壁に対して示す圧力のことです。血液は心臓が収縮した時に送り出され、拡張時に心臓に戻ります。心臓が収縮した時の血圧を収縮期血圧(または最高血圧)、心臓が拡張した時の血圧を拡張期血圧(または最低血圧)といいます。長期の高血圧によって、動脈硬化を引き起こす可能性が高くなります。また動脈硬化が進行すると、眼底出血による視力障害、脳血栓による手足のしびれ、冠動脈硬化による胸痛、不整脈、腎硬化症などが起こります。

脂質異常症
脂質異常症は、脂質としてリン脂質、コレステロール、中性脂肪、遊離脂肪酸の4種類ありますが、これらが血中に多くなり基準値より高い状態です。それぞれ活動維持のために必要な要素ですが、飽和状態になると動脈硬化につながります。自覚症状には乏しく、動脈硬化の進行で脳梗塞や心筋梗塞など将来的に致命的な病気を引き起こす原因になります。「食生活の改善」「運動する習慣づけ」を行うことで改善を図る必要があります。
一度でも健康診断で異常な数値が出たという方は医療機関を受診し、医師の指導に従って数値をコントロールしましょう。

心臓弁膜症
心臓弁膜症とは、心臓の弁が正常に機能しなくなり、血流が悪くなることや逆流するなど心臓のポンプ機能が低下する病気です。
心臓は血液を全身に送るポンプの役割をしており、生命活動に欠かせない臓器です。
この心臓は「右心房」「右心室」「左心房」「左心室」の4つの部屋で構成されており、それぞれの部屋の出入り口に弁がついています。
弁は4つあり、左心室と大動脈を隔てる「大動脈弁」、左心房と左心室を隔てる「僧帽弁(そうぼうべん)」、右心房と右心室を隔てる「三尖弁(さんせんべん)」、右心室と肺動脈を隔てる「肺動脈弁」があります。
この心臓弁があることで、血液が流れるときは開き、流れ終わると閉じます。
しかし心臓の弁が異常をきたすと、血流がせき止められたり、逆流したりすることがあり、結果さまざまな症状があらわれます。
また心臓弁膜症は異常が発生した弁の場所と状態によって、より細かく病名を分類します。
弁が正常に閉じない状態を「閉鎖不全症」といい、逆に開かなくなり血液が流れにくい状態を「狭窄症(きょうさくしょう)」といいます。
例えば大動脈弁が閉じにくい状態にある場合は「大動脈弁閉鎖不全症」と診断されます。

糖尿病
糖尿病は、食事で摂った糖をエネルギーに変えるときに必要なホルモンである、インスリンの異常から起こる病気です。
インスリンの産生や分泌が不足したり、インスリンが十分に働かなくなると、血液の中にブドウ糖が溜まり糖尿病の状態となります。
糖尿病を放置しておくと、網膜症、腎症、神経障害などの合併症が起こります。
食事療法や運動療法、薬物療法などをきちんと行い、血糖値をうまくコントロールして合併症を防ぐことが重要です。

不整脈
不整脈とは、心臓の収縮のリズムが乱れ早くなったり遅くなったりする状態です。期外収縮・体調などの状態などで起こる心配のないものが少なくありませんが、心臓病から起こる場合もあるので注意が必要です。正常な脈拍は毎分60~90位です。
不整脈には、いくつかパターンがあります。大別すると脈が増える頻脈型と脈が少なくなる徐脈です。健康者でも、寝不足やタバコの吸いすぎなどで起こります。時には24時間心電図を装着するホルター心電図が有効です。
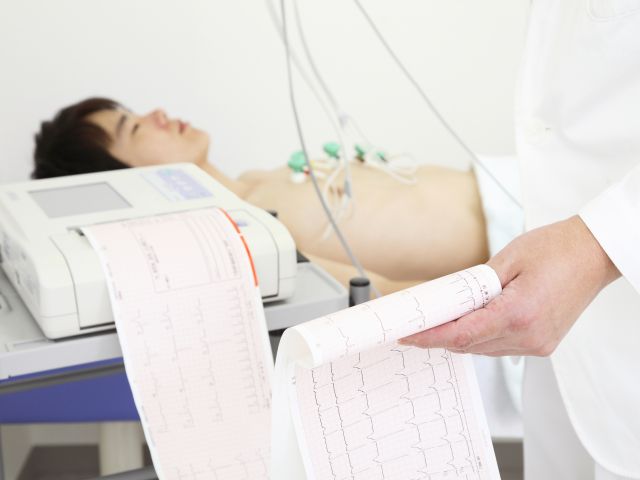
動脈硬化
動脈硬化とは、動脈にコレステロールや中性脂肪などがたまって弾力性や柔軟性を失い、本来の機能を果たせなくなった状態を指し、疾患名ではありません。動脈硬化になると、スムーズに血液が流れなくなります。
動脈硬化が進行すると、心疾患(心筋梗塞、狭心症など)や脳血管疾患(脳卒中、脳梗塞、脳出血など)を引き起こす可能性があります。どちらも、日本における死因の上位を占めています。
動脈硬化の危険因子としては、高血圧・血液中の脂質の異常(脂質異常症)・糖尿病・加齢(男性:45歳以上、女性:閉経後)・喫煙・肥満・運動不足・ストレス・偏った食事内容・嗜好品(アルコール)―などが知られています。
これらの危険因子を多くもつほど、動脈硬化は進行しやすくなります。なかでも、「高血圧」「脂質異常症」「喫煙」は、3大危険因子と呼ばれています。
そのため、動脈硬化を予防するために、定期的に人間ドックなどでLDLコレステロールや血圧をチェックし、適切に管理することが重要になります。また、食事内容、運動不足、喫煙など、いくつかの危険因子は意志次第で改善することができます。
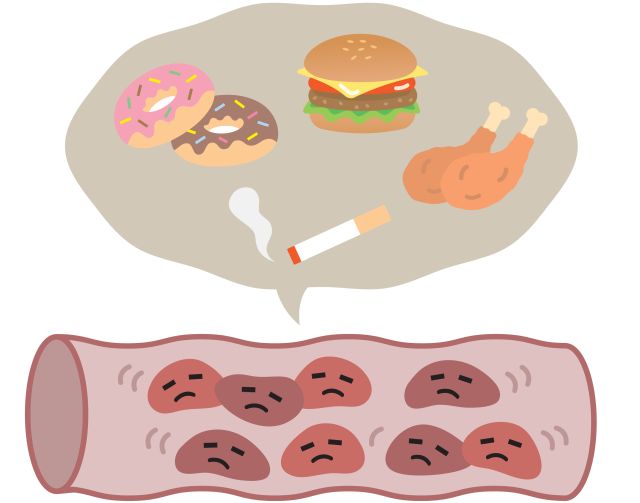
狭心症・心筋梗塞
心臓に酸素を送る冠動脈が動脈硬化などによって狭窄を起こし、心臓の筋肉の収縮に必要な血液(酸素)を送りきれないため、酸素不足をきたして胸痛などの症状を起こす病気が狭心症です。狭窄ではなく閉塞によって途絶するのが心筋梗塞です。50~60歳代に多いですが、40歳代にも見られます。男性に多い疾患です。

発熱などのかぜ症状
- 発熱がある方は検査のタイミングなどの相談をさせていただきますので、来院前にお電話をお願いいたします。
- 発熱がある方の診療は内科でのみ行います。
- 内科は予防接種以外は基本的に中学生以上の診察となります(小学生以下で発熱がある方は小児科を受診するようにしてください。)
- 中学生の診察は内科で行うため、検査等の手技は大人と同様になります。ご了承ください。