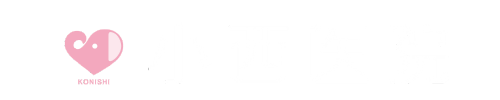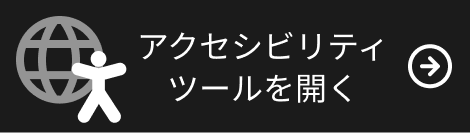- HOME
- 耳鼻咽喉科
外耳炎
外耳炎は、耳の穴である外耳道が細菌に感染し炎症を起こしている状態です。
細菌の増えやすい夏場に多くみられます。
症状は、軽い痛みや痒みから始まり、強い痛み、耳だれなどを起こします。
炎症により、外耳道が閉塞してしまうと難聴、耳閉感、耳鳴りも出てきます。

中耳炎
中耳炎は、病原菌が中耳に入り込み、炎症を起こした状態です。多くはかぜをひいたときの病原菌が耳管(耳と鼻の奥をつなぐ管)から入り込んで感染します。炎症が起きると、粘膜が厚くなり膿が出ます。

難聴
難聴とは聴力が低下している状態のことを指すのですが、ひとことで難聴といってもさまざまな種類があります。
難聴の原因となる部位によって、大きく3種類に分けられます。
伝音性難聴
外耳から中耳にかけての伝音器の障害が原因で起こる難聴です。中耳炎や鼓膜の損傷などから起こる難聴が伝音性難聴です。医学的な治療が可能とされています。
感音性難聴
内耳や聴神経といった感音器の障害が原因の難聴です。加齢による聴力の低下や、長時間騒音にさらされていたことで起こる難聴などがこれにあたります。一般的に医学的な治療による聴力の改善は困難だとされています。しかし、程度に個人差はありますが、補聴器を装用することで聞こえを改善することが可能です。
混合性難聴
伝音性と感音性の両方の症状がみられる難聴です。

鼻炎
鼻炎は、鼻の粘膜が腫れて、くしゃみ・鼻水・鼻づまりを生じます。アレルギーからの鼻炎は、朝・晩が症状が強く、感染からの鼻炎は昼も含め一日中症状が出つづけます。
鼻炎には経過や原因により3つに分類されます。
急性鼻炎
症状から1~3週間で治ります。いわゆる「鼻かぜ」です。
慢性鼻炎
発症から数週間経過しても改善せず、慢性化したものです。
アレルギー性鼻炎
花粉やダニが原因となり発生します。「季節性」と「通年性」とがあります。

副鼻腔炎
副鼻腔炎とは、副鼻腔(鼻の周りにある空洞で鼻の働きを補助する場所)という空洞に炎症を起こして膿がたまってしまったりするもので、いわゆる蓄膿症と言われる病気です。
原因としては、感染・アレルギー・鼻茸・粘膜機能障害・鼻中隔弯曲症(真ん中にある軟骨や骨が曲がっている病気)など色々なものが原因となります。

咽頭炎
咽頭炎とは、俗にいう「のどかぜ」です。咽頭全体が炎症を起こしている状態で、ほとんどの場合、かぜを引き起こすウイルスや細菌に感染したことが原因です。そのほか、有毒ガスや汚れた空気、薬剤を吸いこんだときなどにも起こります。

喉頭炎
喉頭炎(こうとうえん)は、何らかの原因により喉頭に炎症が起きる疾患の総称です。
いわゆる喉の部分にはさまざまな器官が存在し、解剖学的には細かく名称がつけられています。
その中でも喉頭は喉のずっと奥にあり口を大きく開けても鏡で見ることはできません。
声を出す声帯から肺へと続く気管のあたりをいいます。
喉頭が炎症を起こすと、声がおかしくなったり苦しくなったりするのはこのためです。
食べ物の通り道である食道側には咽頭が存在しているため、咽頭炎と共に喉頭が炎症を起こすこともあります。